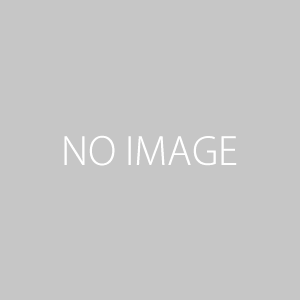昔話 18才の春 その5
1984年7月 学期末コンクール
上達の気配は見られないままだったが6月頃になるとだいぶ慣れた。
一日12時間の集中は無理があると実感したので、
早朝と夜のアトリエに参加する自身への義務を解いて
必要を感じた時だけにすることにした。
デッサンしたり油絵を描いたりしながら暮れて行く毎日は
制作の出来不出来に関わらず爽やかな疲れを連れて来てくれる。
そうこうするうち1学期も終わりが近づき期末テストに相当するコンクールが始まった。
その頃、アトリエに毎日顔を見せる学生は徐々に減って、
100名を切る位になっていただろうか。
寝たきり浪人と呼ばれていた彼らもコンクールとなると
姿を現しアトリエは活況を呈する。
私はコンクールだろうが何だろうがいつも通り、
ただひたすら描いて闘うのみである。
そして3日間かけて描いたデッサン、その提出直前、
どうしても気に入らない画面をパンで全部消して
木炭紙の裏に、10―10≠0 と書いて提出した。
講評会はイーゼルに全作品が並ぶ。
私の作品はひと際目立っている。
私の番になり、「誰だー、このデッサン?」
手を上げると、「あぁ~っ、金子~ォ」と先生方はお困りのハーモニーを響かせる。
少し前、誰かのデッサンの講評の時
「みんな絵が好きなんだろう?画家になりたいんだろう?」と問われ皆が手を挙げる中、
一人だけ手を上げる事が出来なかった私は、頭を抱えた先生方に
「これでいいんです。」と元気な声で答えた。